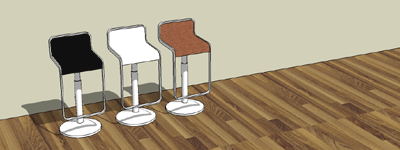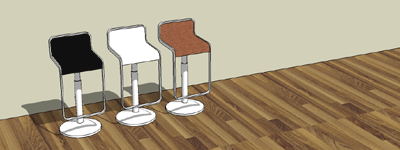|
|
みなさんは土についてどれくらい関心がありますか?
しっかりとした水はけのよい地盤に家を建てることが出来れば良いのですが、なかなかそうは行きません。
軟弱な地盤に住宅を建てるためには、特殊な基礎工事や地盤改良工事が必要になります。
■土地の高さを知る
土地の高さなんて普段の生活の中ではほとんど気にしないで生活していると思います。「あの土地は道路より少し高くなっているな」とか「坂道が多いから疲れるな」くらいは思いますよね。
ここでいう土地の高さとは、海抜・標高のことを言っています。
日本には東京都千代田区永田町に日本水準点という高さの基準があります。これは東京湾の平均海面を0mとした基準値で、これにより日本各地にある水準点に高さが移されています。
自分の住む地域の都市計画課などに問い合わせると、近くにある水準点の高さなどを教えてもらう事ができます。
よく噂などで、「あの一帯は土地が低いから水害になりやすい」、「土地が低いから地盤が良くない」、という声がありますが、参考のために覚えておきましょう。いくら高い土地でも近くに流れる川との高低差がほとんど無い場合や、堤防が低い場合は注意が必要です。
私の記憶では、北海道札幌市では市内を流れる豊平川の水面より、市内中心部の大通り公園のほうが数メートルほど低かったと思います。しかし川の護岸工事を行うことにより、洪水などが起きないようにしてるんですね。
■地盤調査を調査する
地盤の強度を調べる方法には、一般的にスウェーデン式サウンディング試験という試験が行われます。
この試験は小型の試験機を使って行う簡単な試験です。先端がスクリューになった棒に最大100kgのおもりを乗せ、回転されながら棒の沈下量を測定して地盤の強度を測定します。
調査深さは10m程度まで可能ですが、大きな石などが点在する土地では正確な調査ができません。別途にボーリング試験と標準貫入試験を行う事になります。
■N値って?
読み方は「エヌチ」です。地盤の強度を数値で表したもので、数値が多いほど硬い地盤だといえます。上で説明したスウェーデン式サウンディング試験でも、試験結果をこのN値に換算することができます。
また、同じN値でも土質が砂質と粘土では違いがあり、粘土層のほうが良い地盤だといえます。
簡単ではありますが、イメージをつかむ為に表にしてみました。
| N値 |
砂質層 |
粘土層 |
| 0〜3 |
極めて軟弱な層 |
極めて軟弱な層 |
| 4〜10 |
軟弱な層 |
やや緩い層 |
| 11〜20 |
やや緩い層 |
中程度の層 |
| 21〜30 |
中程度の層 |
硬い層 |
| 31〜以上 |
硬い層 |
かなり硬い層 |
その他にも火山灰質のローム層などや、腐植土からなる泥炭地など日本にはいろんな土質があります。
通常は深くなればなるほど硬い層なのですが、数メートル下に比較的固い層があるが、それを抜けると数十メートルも軟弱な地盤が続いてる・・・。という例もあります。関東のローム層でも100mも火山灰が堆積している場所もあるといいます。
|
|